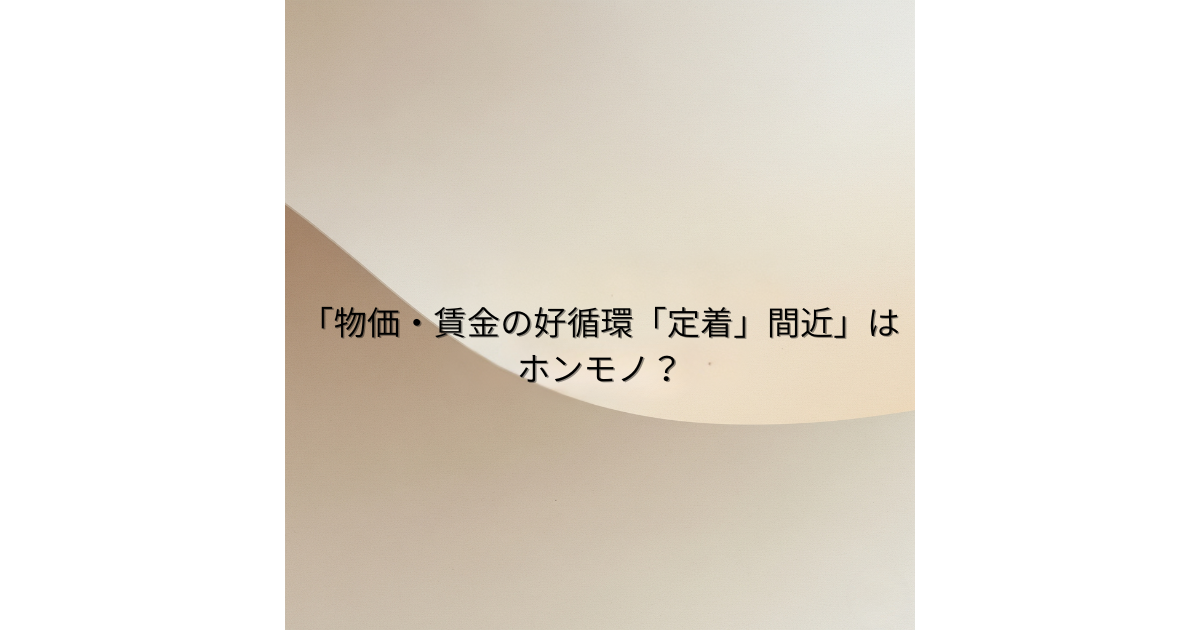2025年度経済財政白書が示す「デフレ脱却」は本物か?賃上げの裏側と持続性への課題
内閣府が本日(2025年7月29日)公表した2025年度経済財政白書は、「賃金と物価の好循環が定着しつつある」と指摘し、日本経済がデフレ脱却へ着実に進んでいるとの認識を示しました。
長らく日本経済を覆っていたデフレからの脱却は、まさに待望のニュース。しかし、この「賃上げ」は本当に持続的なものなのでしょうか?そして、その背景には何があるのでしょうか。
(参考記事:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA285JY0Y5A720C2000000/
この記事では、上記の日本経済新聞記事の概要と筆者の考察を基に解説しています。[日本経済新聞 2025年7月29日付記事](※日経電子版 有料会員限定記事))
なぜ今、賃上げが起こったのか?賃金上昇の3つの背景
白書が指摘する賃上げの背景には、複数の要因が絡み合っています。
- 歴史的な人手不足: 日本の労働市場は、少子高齢化を背景に深刻な人手不足に直面しています。特にIT人材や特定の専門職では、企業が優秀な人材を確保するために、賃上げをせざるを得ない状況にあります。
- 物価上昇の圧力: ロシアによるウクライナ侵攻や歴史的な円安の進行により、輸入物価が高騰。企業はコスト上昇分を製品価格に転嫁し、それが物価上昇へと繋がりました。同時に、家計の生活費増加は、労働者の賃上げ要求を強める大きな要因となりましたね。
- 企業収益の改善: 長引く金融緩和や、一部の大手企業での業績改善も賃上げを後押ししました。内部留保を抱える企業に対し、政府や投資家からの賃上げ圧力が強まったことも見逃せません。
「官製春闘」?この賃上げは政府が後押ししたものなのか
今回の賃上げが、政府の強い後押しによって実現した側面があることは否定できません。
- 「官製春闘」という側面: 岸田政権は、経済界に対し継続的に賃上げを要請してきました。特に経団連を通じた大手企業への働きかけは、今年の春闘で過去にない高い賃上げ率を達成する原動力となりました。
- 賃上げ企業への税制優遇: 政府は、賃上げを実施した企業への税制優遇措置を拡充しており、これも企業が賃上げに踏み切るインセンティブとなっています。
- 「新しい資本主義」の柱: 賃上げを通じた所得の向上は、政府が掲げる「新しい資本主義」の重要な柱の一つです。明確な政策的な後押しが存在するのは確かでしょう。
このように、今回の賃上げは、市場原理だけでなく、政府の強力な政策誘導が大きく影響していると言えるでしょう。
持続的な賃上げには、景気対策と成長戦略が不可欠なワケ
政府の後押しによる賃上げは、短期的なデフレ脱却の動きとしては評価できます。しかし、それが真に持続的なものとなるかについては、まだ多くの課題が残されています。
- 中小企業への波及: 大企業に比べて体力のない中小企業では、賃上げの動きが遅れているのが現状です。日本経済の大多数を占める中小企業の賃上げが実現しなければ、国民全体の所得向上には繋がりません。
- 生産性向上が伴わない賃上げ: 単にコストプッシュ型で賃上げが行われるだけでは、企業の競争力低下を招きかねません。賃上げと同時に、デジタル化投資やDX推進による生産性向上、そして労働分配率の改善が不可欠です。
- 海外経済の不確実性: 世界経済の減速や地政学リスクの高まりは、日本経済に大きな影響を与えます。外部環境の変化に左右されにくい、内需主導の力強い経済成長を実現する戦略が求められます。
今回の賃上げは、デフレ脱却に向けた重要な一歩であることは間違いありません。しかし、政府は短期的な政策だけでなく、中長期的な視点に立った産業構造改革、イノベーション促進、そして労働市場の流動化を促す景気対策や成長戦略を継続的に打ち出す必要があるでしょう。
あなたはこの賃上げをどのように見ていますか?デフレ脱却への期待と、持続性への懸念、どちらが強いでしょうか。